ー【PR】本ページはプロモーションが含まれていますー
つらい気圧頭痛にコーヒーが効くって本当?
飲み方のコツや逆効果になるケース
根本対策と組み合わせるポイントを紹介します
低気圧の日になると
「頭がズキズキしてつらい…」
と感じる人は多いですよね
そんなとき、
身近な飲み物である「コーヒー」が効く
という話を聞いたことはありませんか?
本当に効果があるのか
なぜ効くのか
専門家の見解も交えながら紹介します
気圧頭痛とは?まずは原因を知ろう
気圧頭痛は
天気や気圧の変化によって自律神経や血管が刺激され
頭痛が引き起こされる症状です
気圧が下がると体内の血管が拡張して
脳内の血流量が変化します

その結果、神経が刺激されて痛みを感じやすくなるんですね
日本気象協会などの解説によると
気圧の変化が自律神経のバランスを乱し
「片頭痛」や「緊張型頭痛」を
悪化させることがあるとされています
気圧頭痛の理解は
対策を考える上での第一歩です
コーヒーが頭痛をやわらげる理由
コーヒーに含まれるカフェインが
血管を収縮させる働きを持ち
頭痛の痛みを一時的にやわらげる可能性があります
気圧頭痛の主な原因は「血管の拡張」です
カフェインにはこの拡張を抑える作用があるので
神経への刺激が減少して
痛みが軽くなるんですね
実際に、頭痛薬の多くにもカフェインが配合されています
これは鎮痛成分の効果を高めるとともに
血管収縮による頭痛緩和を狙ったものなんです
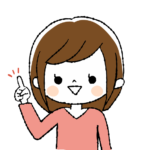
コーヒーを飲むことで
同様の効果を得られる可能性があるんですね♪
•コーヒーのカフェインは、拡張した血管を収縮させることで頭痛を一時的にやわらげることがある
•効果には個人差があり、過信や飲みすぎには注意が必要
•「薬ほどではないが、手軽なサポート策」として取り入れる価値がある
効果を感じやすい飲み方・タイミング
同じ「コーヒー」でも
飲むタイミングや量によって
効果が大きく変わることをご存じですか?
気圧頭痛の緩和を狙うなら
「ただ飲むだけ」ではもったいないんです!
効果を感じやすい飲み方や時間帯
注意したいポイントを紹介していきますね
頭痛が“出る前”や“出始め”に飲むのが効果的
コーヒーは、
頭痛が強くなる前に飲むことで
より効果を発揮しやすくなります
カフェインによる血管収縮効果は
痛みがピークに達してからでは遅く
初期段階で取り入れることで
痛みの進行を抑えやすくなるためです

生理痛がひどくなってから
鎮痛剤を飲んでも効果が出にくい
なんてことはありませんか?
それと同じなんですね
日本頭痛学会の片頭痛対策ガイドラインでも
「痛みの出現初期に鎮痛対策をとること」
が推奨されています
低気圧の日は
頭痛の前兆(肩こり・目の奥の違和感など)
を感じた時点でコーヒーを一杯飲むのがポイントです
1日1〜2杯が目安!飲みすぎは逆効果
効果を狙うなら
1日1〜2杯(カフェイン約200mg以内)
を目安にとどめましょう
カフェインは適量なら血管を収縮させますが
過剰摂取は自律神経を乱し
かえって頭痛が悪化するリスクがあります
厚生労働省やWHOの基準でも
健康な成人のカフェイン摂取量は
1日400mg以下が安全とされています
コーヒー1杯(150ml)に含まれるカフェインは
約80〜100mgなので
1日に2杯程度が安心ラインです
空腹時を避け、ゆっくり飲むのがポイント
コーヒーは、食後や軽食後など
空腹時を避けてゆっくり飲むのがおすすめです
空腹状態でカフェインを摂ると
胃酸が多く分泌されてしまい
胃の不快感や吐き気を引き起こすことがあります
また、一気に飲むと血中カフェイン濃度が急上昇し
神経が過敏になることもあります
内科医や栄養士の見解でも
「コーヒーは胃腸が刺激されやすいため、食後の一杯が最も安全かつ効果的」
とされています
落ち着いた環境でゆっくりと飲むことで
リラックス効果も得られやすくなりますよ
•効果を高めるなら「頭痛が出る前〜出始め」のタイミングがカギ
•1日1〜2杯を目安に、過剰摂取を避ける
•空腹時は避けてゆっくりと飲むことで、体への負担を減らしつつ効果を引き出せる
参考にしたサイト:日本頭痛学会
コーヒーが逆効果になるケースと注意点
カフェインは上手に取り入れれば
頭痛対策の味方になりますが
状況や体調によっては逆効果になることもあります
気をつけたい3つのパターンとその理由をまとめました
飲みすぎると「カフェイン頭痛」を引き起こすこともある
コーヒーを1日に何杯も飲みすぎると
かえって頭痛が起こりやすくなることがあります
カフェインは脳の血管を収縮させる一方
習慣的に摂りすぎると体が慣れてしまい
「カフェイン切れ」のときに
血管が一気に拡張して
頭痛が起こる場合があるんです
脳神経外科などの医療機関では
「1日200mg以上を毎日摂取すると、
カフェイン離脱による頭痛を起こすリスクがある」
と注意を呼びかけています
空腹・寝不足・体調不良のときは刺激が強すぎる可能性もある
空腹や寝不足のときにコーヒーを飲むと
刺激が強すぎて頭痛が悪化することがあります
体が敏感になっているときにカフェインを摂ると
自律神経が過剰に反応して
血管の収縮・拡張が不安定になり
頭痛を誘発しやすくなるためです
医療系の情報サイトでは
「空腹時は片頭痛が起こりやすい」
という記述があったり
「カフェインの過剰摂取が頭痛の悪化因子になりうる」
と医師が解説しています
これらは
「空腹時にコーヒーが直接頭痛を悪化させる」
と断定するデータではありませんが
頭痛が起こりやすい状態にカフェインの刺激が重なると
悪化する可能性があるという注意として
多くの専門家が言及しています
カフェインに敏感な人は少量でも症状が出ることもある
体質的にカフェインに敏感な人は
少量でも動悸や頭痛が出る場合があります
遺伝的な体質や肝臓の代謝速度によって
カフェインへの反応が異なります
なので、人によっては
少量でも交感神経が刺激されて
頭痛や不安感が出ることがあるんです
医療情報サービスでも
「カフェイン感受性には個人差が大きい」
とされていて
体質的に合わない人は控えることが勧められています
•飲みすぎ・習慣化・空腹時の摂取には注意が必要。
•特に「頭痛がひどいとき」「体調がすぐれないとき」は
まず休息・水分補給・軽食などの基本的な対処を優先し
コーヒーは“お守り的な選択肢”と考えると安心
コーヒー以外の頭痛対策も取り入れよう
「コーヒーで少し楽になった」と感じても
それだけで対処しようとするのはNGです
気圧による頭痛は
生活習慣や環境の影響も大きいので
根本的な対策と組み合わせてこそ
効果が出やすくなります
ここでは、実践しやすい3つの方法を紹介します
規則正しい睡眠と食事で「頭痛を起こしにくい体」をつくる
睡眠と食事のリズムを整えるだけでも
気圧の変化に対する頭痛の頻度が減る可能性があります
自律神経は生活リズムの乱れに敏感で
不規則な生活が続くと血管の収縮・拡張が不安定になり
頭痛が起こりやすくなるんです
日本頭痛学会のガイドラインでも
「片頭痛予防の基本は生活習慣の見直し」
と明記されています
特に睡眠不足や空腹は発作の引き金になるため
朝昼晩の食事と睡眠時間を一定に保つことが有効とされています
水分補給と「気圧対策グッズ」で体の負担を減らす
頭痛が起こりやすい低気圧の前後は
こまめな水分補給と
簡単なセルフケアグッズで予防効果が期待できます
脱水状態は血流を悪化させ、頭痛を助長する原因になります。また、耳や首まわりを温めたり気圧変化を和らげるグッズを使うことで、自律神経の乱れがやわらぐためです。
気象と健康に関する研究でも
「水分摂取と体温調整が片頭痛発作の軽減につながる」
という報告があって
市販の「気圧耳栓」や「温熱パッド」は
医師も補助的なケアとして推奨しています
専門医に相談して根本的な治療を目指す
頻繁に頭痛が起こる場合は
自己判断せず一度専門医に相談することが大切です
気圧による頭痛だと思っていても
実は片頭痛や群発頭痛など
治療が必要な病気が隠れている場合があります
頭痛診療ガイドラインでは
「月に数回以上の頭痛がある場合は専門医への受診を検討すべき」
と明記されています
必要に応じて医学的な治療法を組み合わせると
効果が高まるとされています。
•コーヒーは“その場しのぎ”の対処法として有効でも
生活習慣・セルフケア・医療の3本柱と組み合わせることで
より安心して頭痛と付き合えるようになる
・「なんとなく我慢できるから」と放置せず
頻繁に頭痛が起こる場合は一度専門医に相談することが
長い目で見ると一番の近道
気圧頭痛とコーヒーの付き合い方
コーヒーのカフェインには
血管を収縮させる作用があり
気圧による頭痛を一時的にやわらげるサポートになることがあります
ただし、飲みすぎや毎日の習慣化は
「カフェイン離脱頭痛」を引き起こす可能性があるため
1〜2杯程度にとどめることが大切です
空腹や寝不足、体調不良のときは刺激が強く出る場合があり
頭痛が悪化するケースもあるので注意が必要です
睡眠・食事・水分補給など生活習慣を整え
気圧対策グッズや専門医の診察と組み合わせることで
根本的な予防につながります
コーヒーは「つらいときのお助けアイテム」
として上手に取り入れつつ
無理せず自分の体調と向き合うことが何より大切です
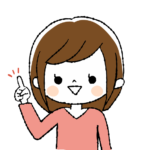
頻繁に頭痛が起こる場合は
自己判断せず一度専門医に相談を!
この記事の内容は、
公的機関や専門団体が出している情報を参考にしています
気になる方は、詳しい内容を下記からチェックしてみてくださいね
•日本頭痛学会:「頭痛の診療ガイドライン2021(PDF)」
•消費者庁:「食品に含まれるカフェインの過剰摂取について」
•日本気象協会:「気圧予報」
・脳神経外科たかせクリニック「気圧と頭痛」
・沢井製薬「頭痛ダイアリー」

最後まで読んでいただき
ありがとうございます
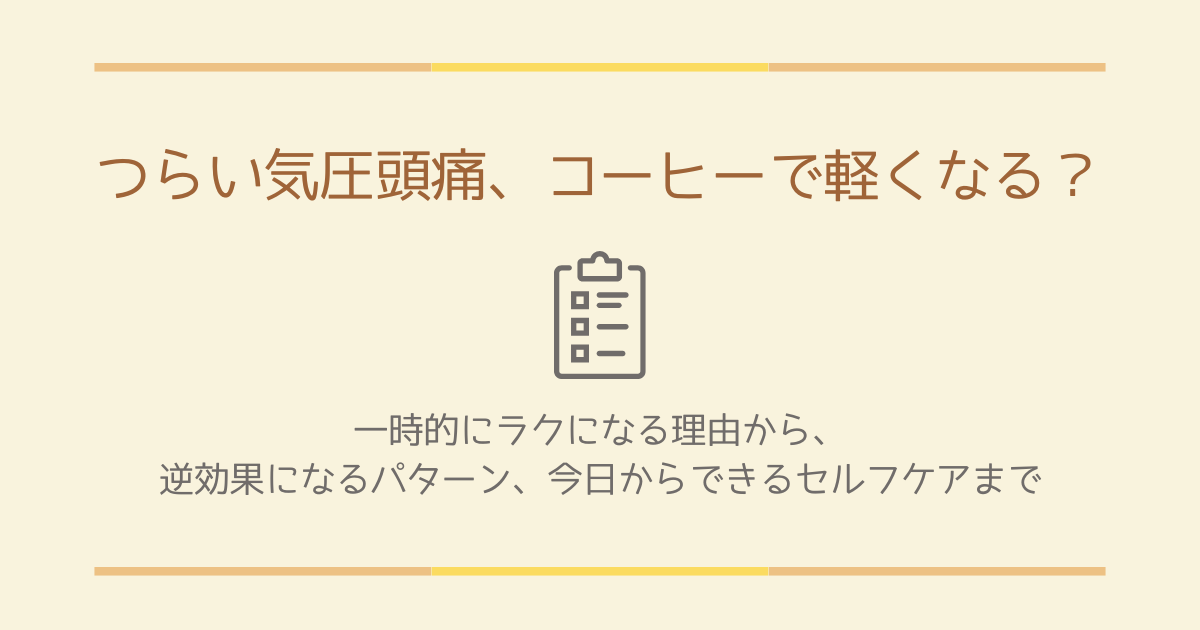



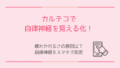
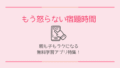
コメント